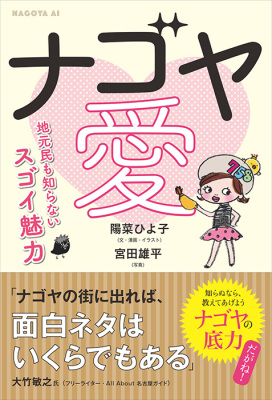update : 2021/03/03 Wed |
�� 




���Υȥ���ġ��2007ǯ7���ꥹ�����Ȥ������ĥ��ĵ������Ѥ߾夲�ƶ���14ǯ��Ĺ�á�
�Ĥ���1000�����ܤȤʤ�ޤ�����
1000�����ܤ�����Ȥ����櫓�ǤϤ���ޤ��������ܥ����ʤ�Ļ�Ҳ𤷤ޤ���
���ܤι�Ļ�Ǥ��륭���ϡ��Ȥä����Τˤ��Ҳ𤷤Ƥ���Τǡ��ͥѡ���ι�Ļ�ǥ�������Ǥ��ä��������Ȥ�����˥������Ǥ���
��������֡ʥ����ʡˤˤϿƤ��ߤΤ���Ļ����������ޤޤ�Ƥ����Ǥ��͡������������顢�����㥯�������奱�����˥�ȥꡢ�饤���祦�����������祦�ʤɡ��Τ��˻��Ƥ롪
�˥�����������
��̾��Lophophorus impejanus
��̾��Himalayan Monal
�����ܥ�����
ʬ�ۡ����ե��˥������������饤��ɡ��ͥѡ��롢�֡������٥åȤˤ����ƤΥҥޥ�仳̮�褤��ɸ��2100��4500m�ۤɤι⻳����©��
�Ѥ�������������Ĥ��оݤȤ��졢��������©�����������Ƥ��ޤ���
������(��åɥꥹ��)�����Ǵ��������ٷ�ǰ�ʣ̣á�
��������70cm���63cm
�νš�����1.98��2.38kg���1.80��2.15kg
���ä���Ȥ����緿�Υ�����
���֡��⻳���ӤˤϤ��ޤ�¤��ʤ����ᡢñ�Ȥ��Ĥ�����3��4���ۤɤξ����ʷ�������褷�ޤ���
�Ұ�ƤϻԤʤ���ͺ����������ޤ���
��ʪ����μ�Ҥ京������ʤɡ�
��ͺ�۷���
�����ϱ�Τ�����å�Ĵ�Υӥ����ɤΤ褦�ʹ�ڤʱ��Ӥ���������̤������˵����ƤȤƤ����������褬˼���Ȥʤ�ľΩ���봧��������ޤ���
��Ϥ�������̣��Ʊ����Ȥϻפ��ޤ���
�������줬�

ͺ�Υǥ����ץ쥤�ʵᰦ��ư�ˤϥ����㥯�˻��Ƥ��ޤ�����Ω�Ƥ�Τ������ˡʥ����㥯��������Τ������ǤϤʤ��������Ȥ������걩�˼���Ļ�ˤ���Ƥ롩

���ܤˤϻ�Ļ�Ȥ���͢�����졤ưʪ��ʤɤǻ����Ƥ��ޤ���
���ܤι�Ļ�������������ι�Ļ��1��
https://hiyoko.tv/torimono/country/eid439.html
����ɤι�Ļ������ɥ����㥯�������ι�Ļ��7��
https://hiyoko.tv/torimono/country/eid490.html
�勵���Υޥ֥������Ҥ褳���åץ뤬�������
https://ameblo.jp/hiyoko-dagane/











 7ǯ�����Υ˥塼������Twitter���Τ�ޤ�����
7ǯ�����Υ˥塼������Twitter���Τ�ޤ�����