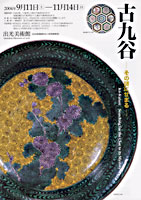 チャイナペイントと呼ばれる、磁器絵付けをしているわたしですが、主に描いているのは、ヨーロピアンと言って、スイスのニヨンと言う土地を発祥とする、ドイツのマイセンや、フランスのセーブルのようなスタイルのもので、そういった西洋磁器の歴史には、多少の知識はあるのですが、お膝元の日本の焼き物には、まるで疎かったのです。
チャイナペイントと呼ばれる、磁器絵付けをしているわたしですが、主に描いているのは、ヨーロピアンと言って、スイスのニヨンと言う土地を発祥とする、ドイツのマイセンや、フランスのセーブルのようなスタイルのもので、そういった西洋磁器の歴史には、多少の知識はあるのですが、お膝元の日本の焼き物には、まるで疎かったのです。しかし、この春に有田を旅してから、俄然日本の焼き物に興味がわき、今回の出光美術館の古九谷の展覧会も、とても楽しみにしていました。でも、「その謎」と言われても、何のことやら、さっぱりだったのです。
古九谷は、都内でも30年以上開かれていないという待望の展覧会なのだそうです。今回の展覧会では、日によって学芸員さんの解説も聞けると言うので、せっかくなので、その時間に合わせて行ってきました。10/28(木)10:30からの回です。思ったよりすごい人で、頑張って近くを陣取らないと、学芸員さんの声も聞き取れないほどです・・・でもすごくおもしろかったです。
その様子はこちらで見られます。まさに、担当はこの写真の荒川正明さんでありました。
『やきものネット・展覧会見て歩き』
******************************************
ここでいう「古九谷の謎」とは何か。それは、いまだ誰がどこで、最初にこの焼き物を作ったのか、はっきりとわかっていないということです。そもそも、九谷焼と言うのは、加賀で1650年代に生まれたものされていたので、その古いものを『古九谷』と呼ぶわけですが、その後の研究で、生産地については諸説あり、肥前有田とする説と、加賀(石川)とする説とが有力で、焼き物と考古学は、切っても切れない関係にあると言えるのだそうです。
九谷には、古九谷の代表的な作風である青手などの絵付けを施された磁器のかけらなどが見つかっていますが、完成品とは、底の型が違っているなどの疑問点があり、有田のほうがやや有力視されているようです。この展覧会での『古九谷』とは、産地ではなく、あくまでも焼き物の一様式としての呼称として認識しつつご覧くださいとのことでした。
1650年代当時、戦国の乱世が終り、江戸の華やかな文化が花開きます。当時の屏風絵には、中世の暗い世相を反映した仏教画とは違い、「ハレ」の盛大な祝宴の様子を描いたものが多く見られるようになります。江戸時代には日常生活の「ケ」と晴れの日の「ハレ」を明確に区別していました。そうした日常とは違うお祝いの席にふさわしい華やかな焼き物として、古九谷は非常に大名たちに珍重されました。
チラシの写真は、古九谷を代表する「青手」ですが、この青手の特徴は、緑(江戸時代は緑を青と呼びました)と黄色の二色で大胆な模様が描かれていること、皿の表面だけでなく、裏など、焼き物全体が塗られていることなどがあります。この頃、日本画の屏風絵には、風景の周りを金で埋める様式が流行します。日本人にとっては、自然はとても大切で敬うべきもの。金で埋め尽くすことは、その自然を敬う、自然へのオマージュであると言えるのですが、この青手の黄色は、その金の部分を現しているのです。
かなりな大皿で、存在感がすごいのですが、当時の絢爛とした屏風や武家の豪華な衣装の前では、これくらいのもので、ちょうどよかったのでしょう。最近評価の高まってる青手ですが、古九谷の中では、五彩手の下とみなされ、重要文化財などの指定を受けたものはないのだとか。すごく古九谷らしいものなのに、なんだか残念です。他にも、中国の挿絵を元に描かれた人物画の食器や、赤絵、祥瑞手、侘びなどの作品が見られ、さまざまな古九谷を満喫できます。
今までも、焼き物を見るのは好きでしたが、こうした歴史や背景を読み取ると、絵画を見るのと同じような面白さがあるのだなぁと思いました。わたしは、九谷の赤絵が好きなので、いつか石川県九谷焼美術館に行ってみたいです。そして、自分でも描いてみたいなぁ、と野望はつきません・・・(笑)
やきものネット 解説より
格調高く豪快な絵模様と大胆な色づかいで多くの人を魅了してやまない、日本最初の色絵磁器「古九谷」。同館では38年ぶり、都内でも30年以上開かれていないという待望の展覧会が、東京・丸の内の出光美術館で開催されています。特別出品の名作10点を合わせ、150点余の優品が全館を使って一堂に公開されているうえ、「古九谷の謎」と呼ばれる産地問題についても、窯跡出土の陶片資料によって研究の現状が紹介されており、力のこもった見応えのある展観となっています。
担当学芸員・荒川正明氏が作品解説したギャラリートークにやきものネット編集部が参加、代わって本展覧会の見どころをご紹介いたします。
初代館長の出光佐三氏は、中国陶磁のコレクションをしていた経緯で、1930年代後半から古九谷の蒐集を始めています。大河内正敏氏を中心に結成された、日本初の陶磁器研究会「彩壺会」が古九谷に注目し、「南京手」「守景手(五彩手)」「伊万里手」「波斯(ペルシア)手」「青九谷手(青手)」など、8つに分類しました。出光氏もそれに従って蒐集した経緯が伺え、まんべんなく網羅している点で、同館コレクションは歴史的に重要な意味を持つと言えます。なお、今回の展覧会で使用する“古九谷”とは、「スタイル」「時代様式」という概念そのものを指しており、「産地」を示すものではないとのこと。「産地については触れておらず、陶片資料を参考に判断いただきたい」と荒川さん。
簡単に、古九谷誕生の経緯をお話ししましょう。
戦国時代から江戸時代初期にかけて、日本は鉱山開発によって経済的に繁栄。中国から輸入された高級色絵磁器が富裕層の心を捉え、茶席や宴席を飾りました。しかし、1640年代に入り、中国の王朝交代に伴う内乱によって輸出が途絶えると、国産の色絵磁器を自前で作る気運が高まってきました。同年代後半には肥前の有田窯、50年代には加賀の九谷窯、備後の姫谷窯(現在の広島県福山市)などで、次々と色絵磁器が開発されるようになりました。
古九谷の特筆すべき点として、径30cmを越える大皿が上げられます。今回約40点を展示していますが、大胆な構図、力みなぎる描線、落ち着いた深みのある彩釉で描かれた、一枚一枚の迫力に圧倒されます。晴の空間を華やかに飾るため、大名たちに珍重されたと思われます。


