おじいさんとの想い出〜ブルーハイビスカス

2004.05.22 Saturday ブルーハイビスカス
アリオギネ(ブルーハイビスカス)
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell(=Hibiscus huegelii Endl.)
アオイ科アリオギネ属
原生地 オーストラリア
常緑低木(半耐寒性)
この花には想い出があります。
(結構長文です(笑))→続きへどうぞ
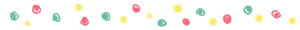


2004.05.22 Saturday スモークツリー
花はとても地味なのですが、
そのあと花の柄が細い糸状に伸びて
花序全体がふわふわと、
煙に包まれたように見えることから、
この名がある。
和名は「カスミノキ」
仙人が、おいしそうに食べていそう、
などと思うわたしは、やっぱり食いしん坊。
我が家はまだ、花をつけていないけれど、
この美しい新芽を見るだけでも
この木がうちにあってよかったと思う。
ところで、四季のスモークツリーの色を比べてみると、
夏のスモークツリーだけ、緑の葉っぱだった。
その後(25日)、雨あがりの初夏の
紫の葉のスモークツリーを撮る事が出来た。
やっぱり、この葉には、雫が似合いますね(^^)
ウルシ科だから、水をはじくのかなぁ。
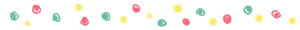

2004.05.22 Saturday オガタマノキ
いい匂いのする植物が好きなのですが
この木は、なんとバナナの匂いがするというので
それはぜひ、買ってみたいと思っていたのだけど
『
カラタネオガタマ』は、どうもイマイチ花が好みでないというので
真っ白な花が咲くという、『
ウンナンオガタマ』を買ったつもりだったのです。。。
が、木が成長して咲いた花が、上の写真・・・どうでしょう?
これ、カラタネオガタマじゃ、ないんでしょうか?
でも意外に可愛い花なので、ま、いいか、と育てています。
花は確かにバナナっぽい匂いがします。もっと大きくなって、
たくさん咲かないかなぁ、と心待ちにしているのです。
カラタネオガタマ(トウオガタマ) 唐種招霊 ←すごい漢字(笑)
モクレン科 オガタマノキ属 Michelia figo (Lour.) Spreng.
原生地 中国 常緑小高木
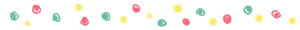

2004.05.29 Saturday マヌカ
少し前の写真ですが、
マヌカ(ギョリュウバイ)です。
毎年、ちょっとずつ木が大きくなって、
ちょっとずつ花が増えて
今年初めて、
こんなにたくさんの花をつけてくれました。
#gardening
続きを読む>>
CSS

このBlogのCSS、わたしが自分でかなりアレンジしたのですが、相当おかしかったようで、Macで見ると、こんな風に、タイトル文字が、画像に重なってたようですね。このCSSを提供してくださった、
『MAC SN』のTSUNOさんから、ありがたくご指摘を受けまして、ちょっといじってみました。
そうそう、我が家のもう一台のマシンは、Win 98なのですが、それだと、BlogPeopleの中身が表示されずに、いきなり、『このサイトを登録』だけ出てて、すっごくへん。原因はなんだろう?Javaを有効にしてないのでは?と言われたんだけど、そんな設定する人、我が家にはいないはず・・・なんだけどなぁ。
続きを読む>>
Cottage Rose

京成バラ園で、バラの苗をひとつ買いました。コテージローズ(Cottage Rose)と言う、イングリッシュローズ。淡いピンクの花びらが幾重にも重なって、クラシカルな感じ。たまたまそこでお会いした方が「これは本当に丈夫よ。たくさん咲くわよ」とアドバイスしてくださったので、買っちゃいました。
あまりいい株でもなかったんだけど、何とかなるかなぁ?ちょっと、時期が遅すぎたみたいです。でも、帰ってから、ネットで検索したら、すこぶる丈夫ということで、わたしでも何とかなりそうです。
これはあまり香りがないのだけが、ちょっと残念。一番欲しいのは、『セント・セシリア』(京成バラ園のローズガーデンで、いろいろ見て、決めました)一番クラシックなイングリッシュローズと言われてるそうです。香りも最高です。秋には、ゲットするぞ〜
#gardening
コモンセージ

このMTを設置して、初めての自分の描いた絵のエントリーです。
本当は、これがメインのはずのわたしのサイトなのですが、気づくと、食べるものばかりになって行ってます。
恐ろしいことです(笑)
わたしが描いているのは、
植物画といって、普通の水彩画とは少し違います。
実物の花を見ながら、特徴を正確に捉え、実物大に描くと言うのが原則です。
ですので、花が咲いてる間に描ききらねばならないと言う、時間との戦いでもあります。
植物画は、かなり時間のかかるもので、ごく小さなもので、3~4時間、
大きいものになると、一年で描ききれずに、数年かけ、のべにして
何十時間もかけて描くことも多いのです。
この絵は、昨日完成したのですが、なんと2000年に描きはじめた絵なのです。
F3ですので、それほど大きな絵でもないのですが、なかなか思うように描けずに
寝かせておいた時間が長かったかもしれないです(^^ゞポリポリ
それが、昨日思い立って描いてみたら、今までになくスムーズに筆が動く。
亀のように歩みの遅い上達振りだと、自分では情けなくなることも多いのですが
それこそ、亀のように、コツコツと努力をすることは、こうして、あるときに
着実に実を結んでいるのを教えてくれます。
それは、感動的な瞬間です。
ひとつのことを、長く続けて努力し続けていると、神様が、ときにこうした
素晴らしい贈り物を、与えてくれるのかもしれません。

我が家の庭のコモンセージ。
コモン・セージ(Common Sage)
シソ科
学名:Salvia officinalis
別名:ガーデン・セージ、薬用サルビア
原産地:地中海沿岸
さて、このコモンセージ。
知ってる方はよくご存知の、ハーブの一種で、
豚肉と相性がいいといわれています。
ソーセージのセージは、このセージから来てるというのは
よく知られていることです。
初夏に咲く、薄紫の花と、銀青緑色の葉のコントラストは
他にない、なかなか素敵な植物です。
続きを読む>>
ハトのチョーカー
鳥についてのblogはじめました!この記事も載せてます。
『トリモノ帖』該当記事
http://hiyoko.tv/torimono/fashion/eid68.html

作ってみました・・・っていっても、金具ちょっといじっただけだけど(笑)
鳥好きなわたしのためにあるようなチャームは大人気で
入ってもすぐに売切れてしまうとか。
吉祥寺の手芸屋さん(ユザワヤではない)で購入。
最近また、ビーズがプチブームなのだ。
一年ちょっと前まで、お店をやってた頃は、
かなり凝ったのが好きだったけど、最近はシンプル志向。
でもそれだと、全然ビーズの在庫が減ってくれないので
たまに凝ったのも作ってみる。それはそれで、楽しいんだけど、
つける機会がないのが、玉にキズ( ̄ー ̄;
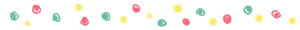

追記:2007/09/07 Fri
さいきんまたブームの兆し。
このところは、つける機会はいっぱいあるが
作る時間がないのが、玉にキズ(笑)
うまく行かないもんザンスね(笑)
80年代に捧ぐ

昨夜、テレビで80年代の音楽を一挙に流していた。
とはいえ、深夜枠であったので、我々は81年で早くも挫折した。
81年と言えば、わたしは小学生。いわゆる歌謡曲を、よく聴いた頃だ。
初めて海外の曲の歌詞を覚えたのは、ノーランズの『ダンシング・シスター』
今でも歌えたのには驚いた。(カタカナで覚えたくせに)
そして、81年を代表する曲と言えば『ルビーの指環』だ。
家族が
「大学に入学するのに、兄貴に下宿先まで車で送ってもらう途中、ずっとこの曲が流れてた」
と言った。大学のある町まで、3〜4時間くらいだったらしい。
それくらい流れてたし、みんな聞いてたし、この曲は、今聴いてもまるで色あせない。
本当に名曲なのだと思う。福山くんのカバーもよかったねぇ。
背中を丸めながら 指のリング抜き取ったね
俺に返すつもりならば 捨ててくれ
男の人のやせ我慢が、せつない。
この曲の詩は、松本隆さん。
はっぴいえんど、というのは、実はよく知らないのだけど、この頃(81年)のこの人の活躍ぶりは目覚しく
松田聖子の詩は、ほとんど担当していた。
なんと言うか、小物使いと言葉遣いが巧みで、言葉のマジックみたいだと、子供ながらに感じた。
でも、映画『微熱少年』の映画は見てないのだけど、原作は読んで、がっかりした。
まるで映画になるのを見越したような、場面作りだと感じた。
確か、斉藤由貴の弟が主演したんだったっけ?
それはさておき・・・
詩を書くようになったきっかけも、もしかしたらこの人・松本隆さんだったのかもしれない。
実際に書くようになったのは、もう少しあとで、中学一年のとき。
友達が作曲して、わたしが作詞で、なんてことをしていた。
今は散文なわたしの詩だけど、あの頃は、ちゃんと『韻』を踏んだりしてたし
一番と二番の歌詞がちゃんと対応してて、みたいなのを書いてた。
心理の巧みさを、感情ではなく、小物の動きや、風景で表すような、そんな詩の世界に、ものすごく憧れた。
80年代は、わたしの小・中・高校時代にまたがる。一番多感だった時代。
だからこの頃の音楽の話になると、止まらない。そんな話は、また今度。
hideさんの
【私のCDコレクション】 Altogether/The Nolans
6/24exblogより移行
博物図譜展 〜博物の肖像画〜

わたしは、ライフワークとして、植物画(ボタニカルアート)を描いている。ボタニカルアートが、植物の肖像画だとしたら、博物画は、この名の通り、博物の肖像画であるといえる。植物画も、博物画の一種である。
武蔵野市立吉祥寺美術館は、吉祥寺伊勢丹の中にある美術館で、美術館と言えるかどうかわからないほど、小さな美術館だと言うことだったけど、なかなか、立派な美術館だった。
今回の企画展以外に、二つの記念室での展示も見られ、なかなか見ごたえがある。これで¥100って、安すぎ・・・(笑)記念室のほうは、4/1〜7/27までは、浜口陽三記念室で、『続・原版にみる浜口陽三の技術』、萩原英雄記念室で『続・萩原英雄60年代の傑作』が見られる。萩原さんのは、抽象的な版画で、わたしには難しすぎたのですが、浜口さんのは、すごい。銅版画メゾティントという技法を使ったアートなのですが、要するに、多色刷りの版画なのだけど、重なって、絵になっていくのが、すごく繊細な技術で、ほおぉぉぉぉぉ〜って感じだった。
さて、本企画展に話を戻すと、わたしも、自分のHPの植物画に関するページに書いてるけど、博物画というのは、真実を写すもの・・・写真技術のなかった時代に、そのものを正確に伝えるために描かれたのが始まりで、それは当然、写真の登場によって、存在意義は失われたように思われるけど、それらの絵は、ただ自然の事物を正確に写したものというだけにとどまらず、芸術作品のような、美しさや輝きを放つものが多いということで、その存在意義の大きさを再認識させられる機会が多くなってきている。
日本の植物学の父と呼ばれる、牧野富太郎博士の神技のような『ムナジモ』の植物図譜、博物画御三家と呼ばれる関根雲停、服部雪斎、中島仰山などの博物画。特に、雪斎の植物の絵は素晴らしかった。仰山の動物の絵も、もちろんすごいし、平木政次の絵の細密さも素晴らしい。これらの絵は、それぞれ高知県立牧野植物園、国立科学博物館、玉川大学教育博物館の所蔵である。余談ではあるが、先日上野の美術館について書いたときに触れたんだけど、上野には、国立科学博物館と、東京国立博物館があって、ちょっとややこしい。これは、このふたつは、途中でふたつに分かれた博物館であり、特に関東大震災で資料をすべて失った科学博物館は、国立博物館に資料を譲り受けて再出発していると言う経緯がある。それで、この二つの間には、今までに何度も資料の行き来があったそうである。
ところで、日本では、植物画=ボタニカルアートという言葉は、随分浸透しているけれど、欧米では、植物図=ボタニカル・イラストレーションと言う言葉と、このボタニカルアートを明確に区別しているそうなのだ。つまり、植物図(ボタニカル・イラストレーション)は、学術的に正確さを極めたもの、植物画(ボタニカルアート)は、そこに芸術的な要素が含まれ、目で見て楽しめるもの。そういった違いがあるそうである。
見ないで描いてみよう!
『花逍遥 〜花鳥風月に遊ぶ』

鎌倉大谷記念美術館に、花の絵を見に行った。こちらは、1995年5月に死去した故大谷米一氏(ホテルニューオータニ前会長・ニューオータニ美術館前会長)を偲んで創設された美術館。デュフィ、ヴラマンクをはじめとする、大谷コレクションを中心に、故人が愛し、長く居住された鎌倉の邸で、公開することとなったそうだ。
---------------------------------------




左/ひっそりとした門構え。もう少し早いと、ツツジが見頃だったようだ。
左中/深い緑と、紅葉のコントラストが、奥へ奥へといざなう。
右中/これが美術館。立派な邸宅はさすが。
右/この扉を開ける瞬間に、ちょっとドキドキ。
最近、日本画が好きで、見ていると本当に落ち着く。美しいコンサバトリーや、吹き抜けの螺旋階段を利用した美術館は、確かに、静かに生活の匂いが息づいていて、その中で鑑賞するとコンクリートの美術館で見るのとは、また違った気持ちで鑑賞できる。
速水御舟の作品に、強く心惹かれた。40歳で急逝した画家だそうだ。画家は、すごく短命か、長寿か極端な気がする。この人の60代、70代の絵が見たかったなぁ、と叶わぬ夢を追いかけてみる。
鎌倉文学館

鎌倉駅の西口と東口を結ぶ通路で、バラの写真に惹かれて、江ノ電に乗って、文学館に行くことにした。立原正秋という方については、ほとんど知識がなく、あまり語ることはできないのだけど、この文学館は、鎌倉を愛し、滞在・居住した文学者たちの紹介、生原稿(複製もあり)、初版本(複製)の展示などがされている。こうしてみると、明治以降の文豪で、鎌倉にゆかりのない人を探すほうが難しいようである。
鎌倉Artな1日
続きを読む(別窓で開きます)>>
1/2 >>
 2004.05.22 Saturday ブルーハイビスカス
2004.05.22 Saturday ブルーハイビスカス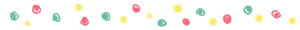

 2004.05.22 Saturday スモークツリー
2004.05.22 Saturday スモークツリー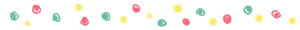
 2004.05.22 Saturday オガタマノキ
2004.05.22 Saturday オガタマノキ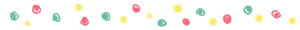
 2004.05.29 Saturday マヌカ
2004.05.29 Saturday マヌカ

 このBlogのCSS、わたしが自分でかなりアレンジしたのですが、相当おかしかったようで、Macで見ると、こんな風に、タイトル文字が、画像に重なってたようですね。このCSSを提供してくださった、
このBlogのCSS、わたしが自分でかなりアレンジしたのですが、相当おかしかったようで、Macで見ると、こんな風に、タイトル文字が、画像に重なってたようですね。このCSSを提供してくださった、 京成バラ園で、バラの苗をひとつ買いました。コテージローズ(Cottage Rose)と言う、イングリッシュローズ。淡いピンクの花びらが幾重にも重なって、クラシカルな感じ。たまたまそこでお会いした方が「これは本当に丈夫よ。たくさん咲くわよ」とアドバイスしてくださったので、買っちゃいました。
京成バラ園で、バラの苗をひとつ買いました。コテージローズ(Cottage Rose)と言う、イングリッシュローズ。淡いピンクの花びらが幾重にも重なって、クラシカルな感じ。たまたまそこでお会いした方が「これは本当に丈夫よ。たくさん咲くわよ」とアドバイスしてくださったので、買っちゃいました。 このMTを設置して、初めての自分の描いた絵のエントリーです。
このMTを設置して、初めての自分の描いた絵のエントリーです。 我が家の庭のコモンセージ。
我が家の庭のコモンセージ。 作ってみました・・・っていっても、金具ちょっといじっただけだけど(笑)
作ってみました・・・っていっても、金具ちょっといじっただけだけど(笑) 追記:2007/09/07 Fri
追記:2007/09/07 Fri 昨夜、テレビで80年代の音楽を一挙に流していた。
昨夜、テレビで80年代の音楽を一挙に流していた。 わたしは、ライフワークとして、植物画(ボタニカルアート)を描いている。ボタニカルアートが、植物の肖像画だとしたら、博物画は、この名の通り、博物の肖像画であるといえる。植物画も、博物画の一種である。
わたしは、ライフワークとして、植物画(ボタニカルアート)を描いている。ボタニカルアートが、植物の肖像画だとしたら、博物画は、この名の通り、博物の肖像画であるといえる。植物画も、博物画の一種である。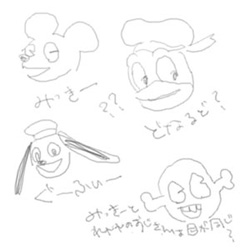






 鎌倉大谷記念美術館に、花の絵を見に行った。こちらは、1995年5月に死去した故大谷米一氏(ホテルニューオータニ前会長・ニューオータニ美術館前会長)を偲んで創設された美術館。デュフィ、ヴラマンクをはじめとする、大谷コレクションを中心に、故人が愛し、長く居住された鎌倉の邸で、公開することとなったそうだ。
鎌倉大谷記念美術館に、花の絵を見に行った。こちらは、1995年5月に死去した故大谷米一氏(ホテルニューオータニ前会長・ニューオータニ美術館前会長)を偲んで創設された美術館。デュフィ、ヴラマンクをはじめとする、大谷コレクションを中心に、故人が愛し、長く居住された鎌倉の邸で、公開することとなったそうだ。



 鎌倉駅の西口と東口を結ぶ通路で、バラの写真に惹かれて、江ノ電に乗って、文学館に行くことにした。立原正秋という方については、ほとんど知識がなく、あまり語ることはできないのだけど、この文学館は、鎌倉を愛し、滞在・居住した文学者たちの紹介、生原稿(複製もあり)、初版本(複製)の展示などがされている。こうしてみると、明治以降の文豪で、鎌倉にゆかりのない人を探すほうが難しいようである。
鎌倉駅の西口と東口を結ぶ通路で、バラの写真に惹かれて、江ノ電に乗って、文学館に行くことにした。立原正秋という方については、ほとんど知識がなく、あまり語ることはできないのだけど、この文学館は、鎌倉を愛し、滞在・居住した文学者たちの紹介、生原稿(複製もあり)、初版本(複製)の展示などがされている。こうしてみると、明治以降の文豪で、鎌倉にゆかりのない人を探すほうが難しいようである。